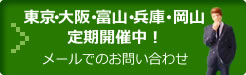2025年2月3日(月)、精考会の埼玉・東京・千葉・兵庫・岡山から11名が参加し、精神の総合医療を実施している成仁病院を見学しました。

病棟看護師による案内で、精神疾患を持つ方の短期集中治療が可能な病棟を視察しました。病棟ごとに工夫が施され、電気通電療法(m-ECT) の実施、刺激の遮断 など、精神科急性期病院ならではの迅速かつ安全な治療と医療体制について担当者から説明を受けました。特に印象的だったのは、様々な職種のスタッフが一人ひとりの患者の状況を深く共有し、誰でも適切に対応できる職能のハイブリット機能が活かされる環境が整えられている点とスペースが広くゆるやかな空気の流れを感じられるところでした。また、職員は、一般職と総合職という2つのカテゴリーによる就業が可能であり、ますます多職種間のハイブリット機能が活かされるという“働きがい”につながる人材資源管理をされていることでした。統計では、平均在院日数は30日、入院時に自殺リスクを評価するスケールに従った重症度管理、トリアージルームでの評価機能など、精神科では新しい仕組みを動かしているところも衝撃的でした。


その後、片山理事長との懇談が行われました。
理事長は、医療や社会のシステムについて、単に「スピードと効率性」を追求するのではなく、本当に解決すべき問題に焦点を当て、既存のルールに縛られず柔軟に対応することの重要性 を指摘されました。従来の「心構え」や「善意」に頼る仕組みの限界にも言及され、特に「心重視の社会が生んだ課題」 について鋭い視点を示されました。
近年、社会全体で「心を重視すること」が正義とされる風潮が強まっていますが、理事長は「それが逆にヘイトに弱くなる要因になっている」と指摘。「寄り添うこと」が優先されすぎると、相手を思いやっているようで実際には一方的な関わりとなり、かえって問題を深める可能性がある という考え方は、非常に考えさせられるものでした。
また、現在の社会では指示や命令を避ける傾向がありますが、行動を明確にし、正すことで「心を考えすぎることなく、安心して取り組める環境」を作ることも重要 だと示唆されました。過度に「心構え」を強調することで、人はかえって迷い、行動できなくなることがあるという指摘には、多くの示唆が含まれています。理事長の考えは、医療の専門家でありながら経営者としての視点を併せ持ち、社会の変化を的確に捉えたものと感じられました。
続いて、インフレがもたらす医療業界への影響 についても重要な指摘がありました。
経済が変化し、人材採用の在り方も大きく変わる中、医療業界はもはや「思い」や「使命感」だけでは成り立たなくなりつつあります。特定の職種に限らず、医療や介護のすべての分野で人材確保の重要性が高まっている のが現状です。
特に、高齢者の増加に伴い、訪問医療や訪問介護のニーズは高まり続けていますが、これらのサービスはコストがかかるため、持続的な運営が難しい という課題が指摘されました。インフレによる人件費の上昇や待遇の格差が広がる中で、人材獲得は一層厳しくなっています。「人を支える仕事をしたい」という思いを持って医療や介護の現場に入ったとしても、より高い待遇を求めて一般企業へ転職するケースが増えれば、これらの分野での人材不足がさらに深刻化する可能性があります。
こうした状況は、病院経営にも大きな影響を及ぼし、特に訪問医療・訪問介護を軸としたサービスは、人手不足によって成り立たなくなるリスクが高い と考えられています。今後、医療機関が持続的に機能していくためには、単なる使命感だけでなく、市場原理を踏まえた戦略的な人材確保と、より持続可能な経営の仕組みを模索する必要がある という示唆がありました。
片山理事長の考えは、単なる医療経営の話にとどまらず、社会全体の構造的な変化を見据えた示唆に富むもの でした。
また、理事長が言う「システムハック」は、一般的な「効率化」や「最適化」とは異なります。「既存のルールにとらわれず、本当に解決すべき問題に焦点を当て、それに応じてシステムを柔軟に動かすこと」 に近い考え方であると感じました。ガイドラインを目的に合わせて単純に動かすのではなく、社会や業界の枠組みを理解し、より本質的な解決策を見つけること を重視しているのが印象的でした。
今回の成仁病院の見学を通じて、医療の現場における革新的な取り組みと、社会の変化に適応するための柔軟な思考の重要性を学ぶことができました。今後の医療業界の在り方について、改めて考えさせられる機会となりました。